こんばんは、ぺいです。

これは次男の卒園式の時の軽度知的障害と自閉スペクトラム症(ASD)を抱える長男。
ちょっと退屈だったみたいですが最後まで座れました。えらい!
今回は前回の記事、真剣に考える障害児育児の親亡き後のお金の話【前編】の続きです。
親亡き後、子供にいかにお金を残すか、です。

今回も結論を最初に述べてしまいます。
【後編の結論】
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)を活用する。
親の死亡又は重度障害後に一口当たり月々2万円(最大2口まで)が子供に終身で、しかも非課税で収入になる。
実際に細かく見ていきましょう。今回も生活の自立の話です。
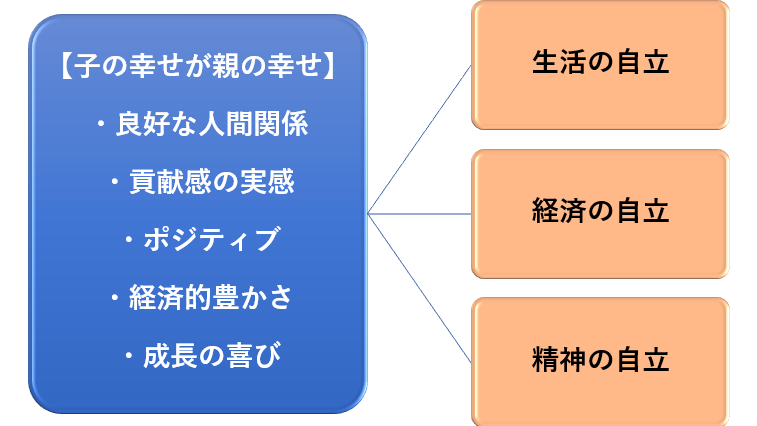
【子供達の障害】
長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生
次男:中度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生
障害者扶養共済制度とは?
障害者扶養共済制度とは親が死亡または重度障害になった場合に、障害のある子供に年金が支給される国の制度です。加入できるのは、一定の障害のある子供とその親で、 受給資格を満たしていれば親の死亡・重度障害時に年金を受け取ることができ、生活資金を確保できます。
メリットが非常に大きく、次のリターンがあります。
【障害者扶養共済制度のメリット】
最大2口まで加入でき、親の死後又は重度障害後に1口辺り、毎月2万円が終身で支給
支給されるお金はなんと所得税、住民税が非課税です
親にとってはその掛金が所得控除になるので所得税、住民税が安くなる(高所得者ほど有利)
生活保護世帯など掛金の減免がある可能性がある(地域差あり)
制度利用の条件
親の条件
①加入年度の4月1日で65歳未満
②生命保険契約ができる程度の健康体であること
子の条件
①知的障害者
②身体障害者手帳1~3級
③精神又は身体に永続的な障害がある人で上記2つと同程度と認められる人
軽度知的障害の長男、中度知的障害の次男は①に該当します。
障害者扶養共済制度の掛け金の支払期間と金額
ここがちょっと複雑なところです。
掛金の支払期間
次のうち、いずれか「長い期間」が掛金の支払い期間です。
(A)65歳になるまで
(B)20年支払継続
(例1)30歳から掛金を拠出し続けた場合⇒(A)35年>(B)20年なので35年間支払続ける
(例2)60歳から掛金を拠出し続けた場合⇒(A)5年<(B)20年なので20年間支払続ける
掛金の金額
加入時の年齢に応じて次の通りになります。
| 加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入 |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
生活保護世帯、住民税非課税世帯など掛金の納付が困難な方等に対して掛金の減免を行っている都道府県・指定都市があるそうです。くわしくは窓口でおたずねください。その方が確実です。
なお、私が済んでいる県の県庁所在地の市では次の通りでした。
<減免基準>
(1)加入者が生活保護世帯に属している場合:全額減免
(2)加入者及びその配偶者が住民税非課税の場合:7割減免
(3)加入者及びその配偶者が住民税所得割非課税の場合:3割減免
繰り返しになってしまいますが、詳細はお住いの市にお問い合わせください。
実際いくら払う?
月単位までは追いません。ざっくりと説明したいと思います。
34歳で一口加入した場合
この場合は約31年毎月9,300円を支払い続けることになるので約350万円弱支払うことになります。
44歳で一口加入した場合
この場合は約21年毎月14,300円支払続けることになるので約360万円支払うことになります。
50歳で一口加入する場合
この場合は20年間毎月18,800円支払い続けることになるので約450万円支払うことになります。
制度の注意点
実質掛け捨ての保険と同じ
解約時に一応の戻りはありますし、子供が先に亡くなった場合も一部戻りはあるのですが、掛金にくらべて僅少です。誤差の範囲程度ですので実質掛け捨ての保険と思って良いでしょう。
制度改悪リスク
実質掛け捨ての保険にもかかわらず、掛金の変更など制度が改悪されるリスクが伴います。
最低20年と考えると無視できないリスクです。
本当に得かはわからない
損得を厳密に予測するのは事実上不可能です。
理由は終身でお金が入る制度ですが、親が、そして子供が何歳まで生きるかはわからないからです。
また、掛金免除制度などで掛金が少なく済むこともあります。
さらに、親には所得税や住民税の控除があるのでそこまで加味したらかなり難しいです。
一応、シミュレーションしてみましょう。
①親が34歳で支払いはじめ、子供が55歳から80歳まで受け取る場合
この場合親は65歳まで一口、累計350万円積み立てることになります。
仮に親の所得税率&住民税率が合計平均20%でずっとあったとすれば実質掛金負担は280万円。
子供が55歳から80歳まで月2万円を受け取るとなると、合計600万円受け取れることになります。
280万円かけて、600万円受け取れるので実質得をしていると考えて良いでしょう。
②親が50歳で支払いはじめ、子供が60歳から75歳まで受け取る場合
この場合は親は70歳まで一口、累計450万円積み立てることになります。
①と同じく、仮に親の所得税率&住民税率が合計平均20%でずっとあったとすれば実質掛金負担は360万円。
子供が60歳から75歳まで月2万円受け取るとなると、合計360万円受け取れることになります。
これだと掛金と受取額が同じ、それならNISA等で運用した方がいいのでは・・・と考える方もいらっしゃいそうです。
障害者扶養共済制度を選ぶなら
以上を考えるとこういう人が合うのかな、と思います。
・公的制度であるため制度改悪リスクはあるものの、安定した給付を期待できることにメリットを感じる
・受取時の所得税、住民税非課税のメリットが大きい
・親の所得金額が高く、減税効果が高い
・前編のNISA口座活用のような相場が上下するのが不安である
・子供の障害が重く、判断能力的に資産運用をさせるのが不安である
・生活保護受給世帯、住民税非課税世帯など掛金の減免を活用できる
・親の年齢的に34歳、39歳、33歳、44歳など掛金が安い年齢を選択可能なタイミングである。
私が障害者扶養共済制度を利用しない理由
私の場合は既に前編で紹介させていただいたNISA口座での資産運用の上、相続にてその資産を子供たちに引き継がせる方法を採ろうと思っています(私が生きている間に子供たちにお金の教育を徹底する)
これによって次の部分はすでに賄えていると思っています。
1.私自身の老後の資金
2.私が死亡した後
障害者扶養共済制度がカバーする部分は上記2の部分です。
ところが上記以外にまだ考えないといけない部分があります。
3.子供が成人し、自ら稼ぐ期間(教育の問題)
4.子供の老後はスタートしているが、私が死亡していない場合のその間(私が長生きした場合を想定)
3については私が直接的に金銭的な支援は原則しないと決めています。
問題は4です。
既に2についての対策はある程度しているわけですから、さらに資金を追加的に2につぎ込むよりは4に備えるべきでしょう。
決して障害者共済制度が悪い制度だから利用しないわけではないですね。
むしろいい制度だと思います。
ただ、限りある資金で1~4までカバーするのにそこまで回せない、というのが私の状況です。
まとめ
結果として自分が利用しない制度を紹介する形になってしまいましたが、私も状況が違っていたら、もしくはこれから変わったら利用する可能性もあります。
実際の資金の捻出をどうするか、それを考える時に一つ使えるのが公的な給付金制度です。
下記の関連記事も是非参考にしてみてください。

それではお互い、これからも頑張っていきましょう!
コメント